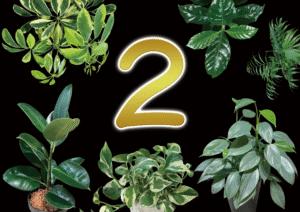ポトスの職員さんは良い意味で私含めマニアックな方が多く、研究熱心で趣味が多く、話していて楽しい方々がそろっています。
そういえば昨年だったかな、事業所の近くの交差点で信号機の交換作業が行われていました。
大きなクレーンが伸び、作業員さんが高いところで手際よく信号機を付け替える姿は迫力があり、なかなか普段見ることができない光景でした。
ちょうどお昼時だったので、利用者さんに「見に行ってみる?」と声をかけたのですが、
「暑いからやめときます」
との返答が多数。。。
確かに真夏の日差しの下に出るのは大変です。
結局、私ひとりで見学することにしました。(暑さ忘れるくらい面白いのになぁ~と思いながら)
何度も見たことはありますが、作業は私からすると『テーマパークのスペシャルショー』のようで、
古い信号機が外され、新しいものが設置されていく様子は見応えがありました。
「こんなふうに安全が守られているんだなあ」と実感しつつも、
やっぱり古い信号機が今までこの交差点の安全を守り続けてきて役目を終えたんだなと思うと、まるで英雄のようで、とても切なくなります。

今回新たに設置された信号機は、【低コスト型のフラット式LED灯器】
実はこの灯器、全国的に導入されていますが、東京都だけ導入されていなかったのです。
理由として、各都道府県には信号や交差点・道路の構造に関する基準書というものがあり、
工事を実施する際、施工業者は基準書をもとに行政から依頼された工事を実施します。
東京都の場合、基準書にこの低コスト型のフラット式LED灯器がマッチしていなかったから、と言われています。
LED灯器は、従来の電球式に比べ視認性・西日による疑似点灯(西日が信号のレンズ内に差し込むことでレンズが光ってしまい、
通行者から見た時に赤なのか青なのかが判別しづらくなる現象)が起きず、電力消費も少ないため、全国的に導入が進んでいます。
個人的には、やはり昭和~平成初期に作られた電球式の信号灯器のほうが、様々な交差点内の事情をクリアするために工夫されているもの
(例えば庇(ひさし)と呼ばれる、レンズの上についている屋根のようなものが長かったり、信号機自体がビックサイズであったり等)が
多く設置されていたので、「あぁ、こういった理由があってこういう信号機になっているんだな」と想像したりもして楽しいです。
と、まぁ私も信号機に関してはマニアックなので、これぐらいにしておきますが。
こうやって自分の好きを発信していくと、聞いてくれる人も時々いるので(笑)
ぜひ、あなたのお近くにある信号機を眺めてあげてください。
きっと素敵な発見があるかと私は思いますよ。
素敵な信号機ライフをぜひ、お楽しみくださいね。